専門外来

漢方内科外来
漢方内科は診療範囲のとても広い科です。内科疾患を始めとして、産婦人科や皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科などの他、外科領域の疾患にも漢方薬を処方しています。精神を含む体全体を診て処方しますので、あらゆる疾患が治療対象になります。温泉療法の専門医もおります。
症状例
体がだるい、食欲がない、イライラする、やる気が起きないなど、検査結果は正常です、と言われるいわゆる不定愁訴。現在○○で通院服薬中だが、中々症状がとれない、再発しやすい。癌などの術後、風邪をひきやすいなどで免疫力をアップさせたい、など、多種多様です。
診察の流れ
漢方医学的な問診票に記入していただきます。診察は眼の病気であっても必ずお腹を触ります(切診と言います)。脈診、舌診、望診など漢方医学独自の診察を行います。この時、西洋医学的情報は非常に重要ですので、今までの検査結果は是非持参してください。

漢方薬といえども副作用が出る場合がありますので、定期的な採血が必要です。
風邪の治療などは速効性が期待できますが、長年患ってきた症状を改善するためには数か月必要なこともあります。
漢方内科 診療時間・担当医のご案内
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 |受付:8:45~11:30 |
安川 | 大塚 ・安川 |
大塚 ・安川 |
安川 | 安川 | |
| 午後 13:30~17:00 |受付:13:15~16:00 |
安川 | 大塚 | 安川 | 大塚 | 安川 |
※第2・4火曜日 安川医師
※大塚医師の外来は事前予約制となります
担当医
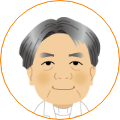
- 漢方内科医
- 大塚吉則
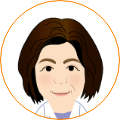
- 漢方内科医
- 安川香菜
糖尿病内科外来
糖尿病は主な症状もなく、急に悪化する疾患ではありません。
ですが、そのまま放置していると徐々に進行し、合併症による失明や、透析に至ることもある恐ろしい病気です。
しかし、早くから適切な治療をすることで、特に症状も出ず、健康に寿命を全うすることも十分可能な疾患です。
健診などで糖尿病が疑われた方、糖尿病が気になる方、また薬やインスリン注射に不明な事がある場合もお気軽にご相談ください。
「糖尿病」は、患者様と医師だけで治療するのではなく、栄養士・看護師・薬剤師などの多職種のスタッフと一緒にチームを作り、患者様の疑問に答えサポート致します。
診療の流れ
診察は、電話(TEL:011-783-5100)での予約が必要です。
診察前に、血圧・体重測定。採血・尿検査の結果が出てからの診察になります。
糖尿病内科外来 診療時間・担当医のご案内
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 |受付:8:45~11:30 |
||||||
| 午後 13:30~17:00 |受付:13:15~16:00 |
大塚 |
※大塚医師の外来は事前予約制となります
担当医
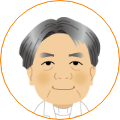
- 糖尿病内科指導医
- 大塚吉則